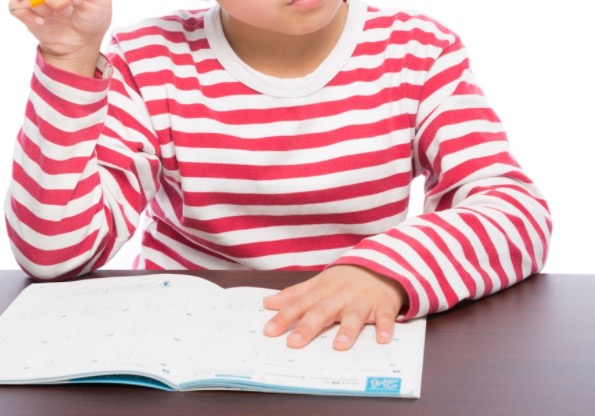知能検査の結果は数値として表されます。WAISⅣまたはWISCⅣという知能検査では、基本的に以下の5つが数値化されます。
・IQ(検査の問題の総合得点のようなもの)
・言語理解
・知覚推理
・ワーキングメモリー
・処理速度
知能の中には、いろいろな種類の性質があります(言葉の意味を理解する性質、目で見る情報を理解する性質などなど)。そして、「どの種類のものがどのくらいすぐれているのか」を示しているのが「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」の4つの指標の数値です。
ただし、IQと4つの指標の数値を見るだけでは、その人の具体的な特徴はほとんどわかりません。なぜなら、数値が示しているものはあくまでも「検査の問題がどのくらい多く解けたか」であって、「どのような正解の仕方や間違え方をしたか」は、数値を見てもわからないからです。そして、ひとりひとりの知能の具体的な特徴は、まさにその「正解の仕方や間違え方」に表れるのです。
たとえば、「知覚推理」の数値が110(平均よりも高め)の人が2人いたとします。2人とも同じ数値ですが、「正解の仕方」に以下のような違いがあった場合、2人の特徴は決して似ているとは言えません。
Aさん…かなり難度の高い問題以外はほとんど正答できていたので、知覚推理が110になった
Bさん…かなり難度の高い問題でもたびたび正答していたが、そのかわり簡単な問題で
見落としによるうっかりミスをすることも多く、知覚推理が110になった
この場合、Bさんの方がAさんよりも、「集中力にムラがある」という特徴が強そうです。解けた問題の多さはAさんもBさんも同じくらいなので、知覚推理は同じ110になっていますが、2人の間には明らかに特徴の違いが見受けられます。
もし Bさんの知能検査の結果の報告書に、IQと4つの指標の数値しか書かれていなかったら、「Bさんは集中力にムラがありそうだ」という具体的な特徴はわかりません。そうなると、せっかく知能検査を受けたのに、「知覚推理が高い? 推理力が高いのかな?」といったような、ものすごく漠然としたとらえ方しかできなくなってしまいます。
このため、知能検査の結果の報告書には、数値だけではなく文章による説明が必要です。「〇〇さんはこのような正解の仕方をしていたため、△△△△のような特徴があると見受けられます……」という文章があってこそ、報告書は特徴をくわしく理解する手がかりとなりうるのです。
※ 本エッセイは継続的に更新されます。毎回、発達障害やそれに関連するお悩みをテーマとし、そのお悩みの理由や対処法を考える上で役立つ知識・考え方などをご紹介いたします。