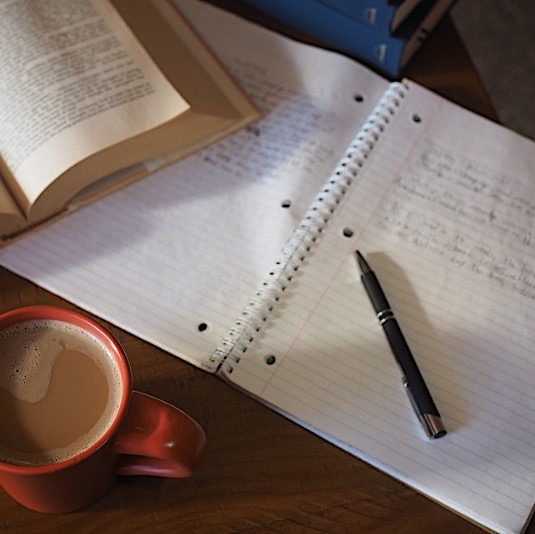当センターでは、「知能検査を受けたい(または子どもに受けさせたい)」という方々に、「いきなり知能検査を受けてもらうこと」は原則として行いません。基本的に必ず、「検査前の話し合いの時間」を取ります。
その話し合いの主な目的は、以下の2点です。
①「知能検査の実施が、その人の支援に必要かどうか」を、心理士が判断すること
知能検査はあくまでも、「何か困っていることがある人」を支援するための手段にすぎません。このため、「困っていること」を改善するために、知能検査以外の手段の方が役立ちそうであれば、知能検査にこだわる必要はありません。
人によっては、「知能検査は必要ない」どころか、「今、知能検査を受けると、事態が悪化する」という場合もあります。
例えば、精神的にかなり不調であるときに知能検査を受けてしまうと、その人の知能は正確に調べられません(不調時は検査の問題を解く力を発揮しにくくなるからです)。なおかつ、不調時は、「検査の結果説明を冷静に聞くこと」も難しくなります。このため、結果説明を受けたときに、
「結果の点数が低かった。ということは、自分はいろんなことがうまくできない人間なんだ……」
といったふうに、説明の内容を過剰にネガティブに受け取って、ますます精神状態が不安定になる場合もあります。
そのような事態を防ぐために、「知能検査の実施が本当に必要なのか、あるいは実施しない方が望ましいのか」について、じっくり検討しなければいけないのです。
②心理士が、検査を受ける方々に、「知能検査の大まかなイメージ」を伝えること
「知能検査とはどのような検査なのか」について、検査を受ける方々がある程度正確なイメージを持てていなければ、検査を受けたあとで「検査結果の内容を誤解する」ということが起こりえます。
例えば、「知能検査で仕事や勉強の能力の高さがわかる」というのは、間違ったイメージです。もしそのイメージが強ければ、例えば検査結果の点数が少し低めであるだけで、「自分は仕事ができない人間なのだ」と誤解してしまいます。そのような誤解を防ぐために、心理士が前もって、「知能検査とはだいたいこういうものです」という説明をする時間が必要なのです。
急いで知能検査を行うことが「よいこと」とは限りません。検査を有意義なものにするためには、慎重に話し合う時間が重要です。
※ 本エッセイは継続的に更新されます。毎回、発達障害やそれに関連するお悩みをテーマとし、そのお悩みの理由や対処法を考える上で役立つ知識・考え方などをご紹介いたします。